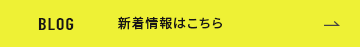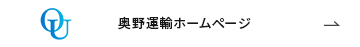月別アーカイブ: 2025年6月
ポーテックのよもやま話~第10回~
皆さんこんにちは!
株式会社ポーテック、更新担当の富山です。
コンクリート二次製品・布設・緊張工事の鉄則5ヵ条
~安全・精度・効率を追求するための基本とは~
前回の記事では、コンクリート製品や布設・緊張工事の歴史についてお話しました。
今回はその続編として、**実務で必ず押さえておきたい「鉄則5ヵ条」**を、現場視点でご紹介します。
現場は常に“生もの”です。条件や環境は刻一刻と変わります。だからこそ、どんな現場でもブレずに守るべき「基本の鉄則」を持つことが、事故ゼロ・高品質な施工への第一歩です。
鉄則①:“事前確認・すり合わせ”が最重要
据付位置、部材寸法、搬入ルート、重機の旋回範囲、地中埋設物の有無など、施工前の確認が命です。
「ちょっとズレただけ」「思っていた位置と違った」が、数センチの誤差で構造的致命傷になりかねません。
現場での“即断即決”を避け、図面と現地の整合性をしっかり確認し、関係者で共有することが、全ての基本です。
鉄則②:“レベル出し”と“基礎調整”を妥協しない
布設工事では、いかに正確に水平を出すかが重要です。
たとえ製品そのものが高精度であっても、下地の転圧不足や不陸調整の甘さがあると、後に大きな沈下・ひび割れの原因となります。
基礎地盤の締固め、路盤調整材の選定、レベル測量など、**「見えなくなる部分こそ丁寧に」**が鉄則です。
鉄則③:“安全帯・合図・死角”を徹底せよ
布設作業や緊張作業は、重量物の吊り上げ・高所作業・高圧作業など、災害リスクの高い工種です。
事故の多くは「合図が伝わっていなかった」「死角から人が入っていた」「声をかけたつもりが聞こえていなかった」といった“すれ違い”から起こります。
KY活動、声出し確認、作業員間の目配せ・合図、そして**「安全帯を義務化し、使い方まで徹底」**することが必須です。
鉄則④:“緊張作業”は“段取り8割、施工2割”
PC鋼材の緊張作業は、施工後に戻せない作業です。
定着アンカー・導入力・グラウト充填・養生管理まで、すべての段取りと管理が仕上がりを決めます。
ケーブルの通りや防錆処理、トルク管理、張力計測値などは「記録にも残る」ため、第三者にも説明できるよう、一つひとつのプロセスに根拠を持つことが重要です。
鉄則⑤:“天候・施工環境”を侮らない
雨天での布設、夏場の高温下での緊張、冬季のグラウト凝固遅延――すべてが品質に影響します。
現場では“工程通り”に進めたくなる気持ちは分かりますが、コンクリートや鋼材は気象条件に敏感です。
現場判断で「やめる勇気」も品質確保の大前提。天候・温度・湿度を常に意識し、「人・材料・機械のコンディション」を最良に保つことが求められます。
■ まとめ:鉄則を守る者だけが、“安全と信頼”を手にする
土木やインフラの世界では、「誰も気づかないほど当たり前に機能する」ことが最高の成果です。
その“当たり前”をつくるためには、こうした鉄則を一つもおろそかにせず、丁寧な段取りと技術の蓄積が必要です。
目立たないけど、なくてはならないこの工事分野。だからこそ、真面目に、誠実に、鉄則を守る人たちが輝きます。
次の時代の基盤をつくる仲間たちへ、これらの鉄則が届けば嬉しく思います。
次回もお楽しみに!
株式会社ポーテックでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()
ポーテックのよもやま話~第9回~
皆さんこんにちは!
株式会社ポーテック、更新担当の富山です。
コンクリート二次製品・布設・緊張工事の歴史:インフラ整備と共に歩んだ技術の進化
今回は「コンクリート二次製品」「布設工事」「緊張工事」の歴史について、建設業のインフラ技術の進化をたどる視点でご紹介します。
私たちの暮らしを支える道路、橋梁、上下水道や造成地の裏側では、これらの技術が長年にわたって発展を遂げてきました。なかなか表舞台に出ることは少ない領域ですが、縁の下の力持ちとしてなくてはならない工法たちです。
■ コンクリート二次製品のはじまり:現場打ちからプレキャストへ
コンクリートは古くローマ時代から使われてきた建材ですが、日本において本格的に使われ始めたのは明治以降です。初期は「現場打ち」が主流で、型枠を組み、その場で生コンを流し込む方式でした。
しかし、昭和30年代以降の高度経済成長期になると、工場であらかじめ成形された「コンクリート二次製品(プレキャスト製品)」の需要が急増します。
電柱・側溝・擁壁・ヒューム管・カルバート・U字溝などが量産され、現場での作業効率や品質安定の面からプレキャスト方式は急速に広まりました。
これにより、工期短縮・コスト低減・品質安定が実現され、特に公共工事や都市インフラ整備において中核を担う存在となっていきます。
■ 布設工事の進化:手作業から重機と効率化へ
「布設」とは、コンクリート製品を所定の場所に据え付ける工事のことです。
昭和の中頃までは人力と簡単な滑車などで据付ける場面も多く、大変な重労働でした。
やがて昭和後期から平成初期にかけて、油圧ショベルやラフタークレーンの普及により、布設工事は“重機化”の時代へと移行します。熟練工の勘と経験に頼っていた時代から、図面に基づいた高精度な位置決め・レーザーレベルや計測機器を用いた施工が主流になり、安全性と生産性が格段に向上しました。
また、近年ではICT建機やBIM/CIMによる「施工の見える化」が進み、布設工事においてもデータ活用が浸透し始めています。
■ 緊張工事(プレストレストコンクリート)の登場と革新
「緊張工事」とは、プレストレスト・コンクリート(PC工法)における作業の一環であり、鋼製のPC鋼材を緊張(引っ張り)した状態で固定し、コンクリート構造物に高い耐久性とたわみに対する抵抗力を持たせる技術です。
この技術は、戦後日本の橋梁建設に革命をもたらしました。昭和30年代以降、従来の鉄筋コンクリート(RC)に比べて長大スパン・高耐久・軽量化を実現できるPC構造は、高速道路や高架橋、床版、張出し構造などに多用されるようになります。
平成以降は「後施工PC」や「グラウチングの高性能化」、さらには「プレキャストPC部材」の量産化なども進み、品質と施工性の両立が実現。近年では耐震補強や老朽化対策としてのPC緊張工事のリニューアル需要も増えています。
■ まとめ:インフラの礎を築いてきた静かな主役たち
コンクリート二次製品・布設工事・緊張工事は、いずれも目立つ存在ではありません。
しかし、都市機能やライフラインを支えるこれらの技術がなければ、私たちの生活は成り立ちません。
これからの時代、高齢化や人手不足、脱炭素、SDGsの波の中で、これらの分野はさらなる進化が求められています。次回は、その進化を支えるために大切な「鉄則」について深掘りしてまいります。
次回もお楽しみに!
株式会社ポーテックでは、一緒に働いてくださる仲間を募集中です!
私たちが採用において最も大切にしているのは、「人柄」です。
ぜひ求人情報ページをご覧ください。皆さまのご応募を心よりお待ちしております!
![]()